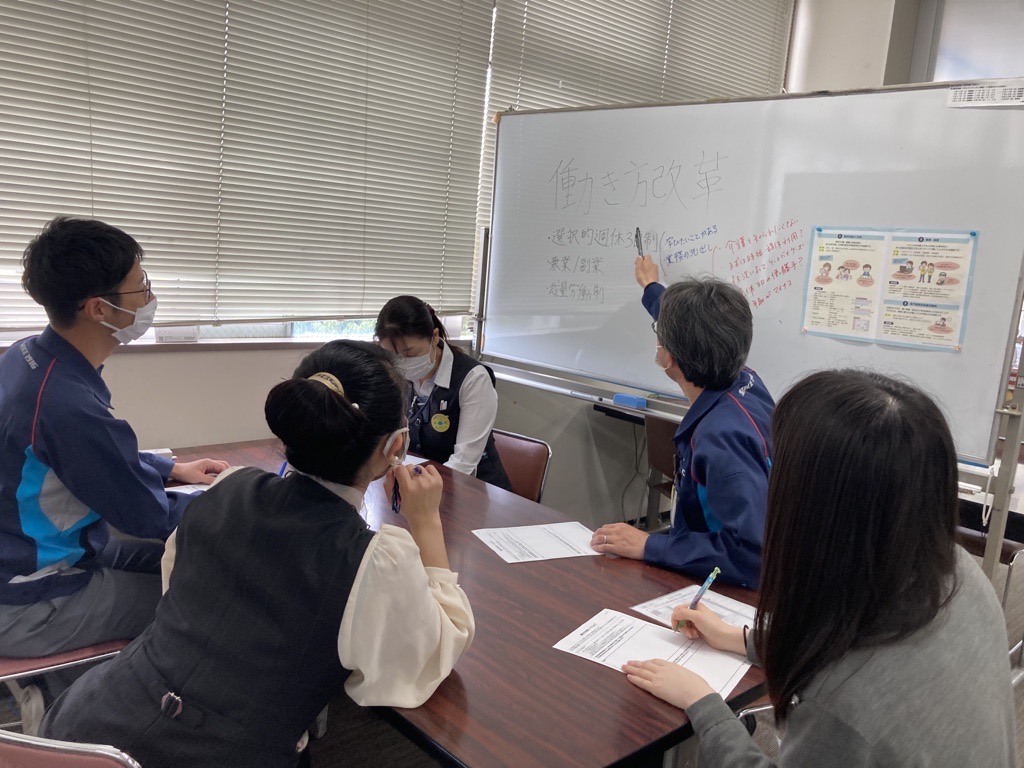◉この記事の概要
従来の当たり前の枠を超え、新しい働き方を選択できるよう2022年度に導入された「兼業副業」「選択的週休3日制」「裁量労働制」の3制度。社内でも少しずつ利用が広がり、最近では柔軟な働き方ができることに魅力を感じて入社を希望される方も増えています。この制度導入の背景にはどんな目的があったのか、導入から3年を経て新たに見えてきた課題はあるのか。制度設計から携わってきた人事戦略部の藤田さんにお伺いします。
◉この記事の見出し
- 「働きやすい職場」で、終わってしまってはいないか?
- 一番時間をかけたのは、考え方を変えるためのコミュニケーション
- 子どもに気がかりを残したまま、働かなくてもいいように
- 変革とは、レッテルを剥がすこと
- 究極は、パーパスだけでいいはずだ
◉お話を聞いた人
藤田 大祐(ふじた だいすけ)
㈱ソミックマネージメントホールディングス 人事戦略部タレントマネジメント室。2020年に入社。前職、社労士事務所時代に企業(他社)の人事制度をつくる中で、「制度導入後にその会社がどうなったのかまで知りたい」と思案。働き方改革の推進や、採用、教育・育成、企画など、人事業務を幅広く行っている。
「働きやすい職場」で、終わってしまってはいないか?
2022年度から導入された「兼業副業」「選択的週休3日制」「裁量労働制」の3制度。これらを含む働き方改革の推進が社内で持ち上がったのは、制度導入前年の2021年のことだったと藤田さんは話します。

藤田さん
従業員がよりチャレンジできるような環境を整えたいというのが元々の趣旨で、その一つとして柔軟な働き方を生み出せるよう改革を進めてほしいという打診が経営層からあったんです。つまり最初から制度導入ありきではないんですね。私も最初は日常業務の延長線上でいろいろな方にヒアリングを行い、みんながもっとチャレンジできるようになるには何が必要かを考えていきました。
ヒアリングをする中で、「ソミックは確かに働きやすい。でもそれだけでいいのか?」という声をよく聞いた藤田さん。働き方に満足して終わっている人が多いのが課題だと感じたそうです。
藤田さん
“働きやすい”ことは大切ですが、そこから“働きがい”を一人ひとりが獲得するには、個々人が自分にとって成果の出しやすい働き方を前向きに模索する必要がある。こうした考えから、自分の働き方や仕事観を改めて考え直し、新しいことに踏みだすきっかけにつながるものとして前述の3制度に焦点を定め、組合との合意形成をとっていきました。
一番時間をかけたのは、考え方を変えるためのコミュニケーション
導入する制度を定めてから実際の運用までには、約一年の時間がかかっています。その一年間は主に、現場への制度の落とし込みや周知活動を行っていたといいます。
藤田さん
制度の中身が大体固まってから、各部署でワークショップを行ってもらいました。『同僚が週休3日を使ったら、休んだ1日分の仕事は誰がどう分担するか』というような、具体的なケースを想定して話し合ってもらいましたね。もちろん周囲の誰かではなく自分が使う前提で考えてもらうようにも人事から働きかけました。
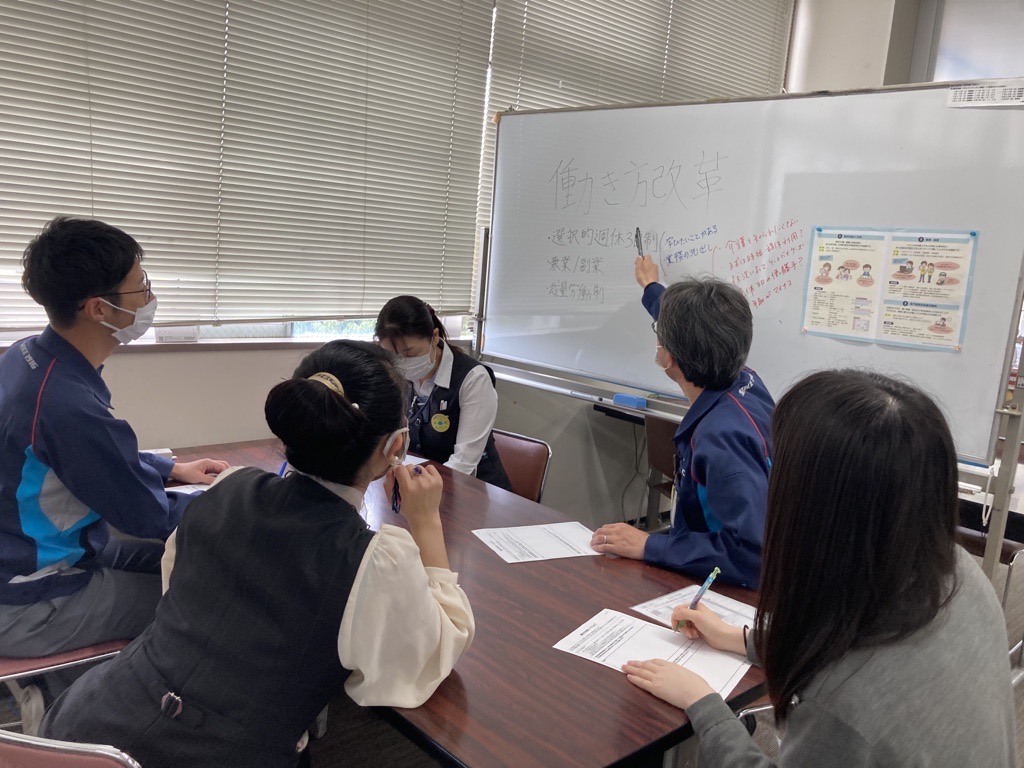
導入にあたり最も壁に感じたのは、従業員たちの中にある「労働とは、一日8時間×週5日行うものだ」という固定観念だったと話す藤田さん。
藤田さん
裁量労働制はともかく、週休3日や兼業副業なんて製造業でやるのはありえないという人が多かったんです。おそらく制度をつくって導入するだけなら半年もかからないんですが、こうした考え方を変えていくためのコミュニケーションには特に時間をかけたと思います。ただ、最初に丁寧に合意形成ができれば、あとはスムーズに進みました。ソミックはやると決めたらやる人が多い会社なんです。それはすごくいいところだと思います。
子どもに気がかりを残したまま、働かなくてもいいように
制度が導入されて、約三年。裁量労働制の利用者は多く、兼業副業と週休3日もそれぞれ利用者が入れ替わりながら常に10人ほどが利用しているそうです。利用する際には職場の上司に承認を得ればOKで、人事が介入することは基本的にありません。
藤田さん
まだ利用者がすごく多いわけではないからかもしれませんが、現状ほとんど問題は起きていません。調整が必要なことがあるとすれば、同じ職場で週休3日の利用希望者が固まってしまった場合には、多少の異動を組むことくらいでしょうか。
現状、週休3日制の利用には「育児、介護・看護、学び直し、 治療・リハビリ」という申請理由の制限が設けられています。最も多い申請理由は育児と介護。それらに従事する女性たちが多く集まる工場では、制度利用者が増える傾向にあるのだそうです。
藤田さん
『週休3日と兼業副業制度の併用をしたい』など、使い方の拡充を求める声はありますが*、今のところ制度への反対意見はなく、『制度で助かっている』という声が多いですね。お子さんのことで気がかりを残したまま仕事をしてもパフォーマンスは上がらないでしょうし、良い仕事をする上での心技体を整えていくという意味では、すでに意味のある制度になったと感じています。
*2025年3月現在は併用できません。裁量労働制と兼業副業制度は併用可能です。
変革とは、レッテルを剥がすこと
これから人事制度をどのように展開・充実させていきたいかを藤田さんにお伺いすると、「まず、ここまでの反省点があるんです」という答えが返ってきました。
藤田さん
今回の制度導入の目的は、『自分が最も成果をあげられる働き方を一人ひとりに考えてもらうこと』でした。ごく単純に言ってしまえば、朝働く方がいいか、夜働く方がいいかは人それぞれ違うはずなので、そうしたことを個々人が模索した上で自律的な働き方を見つけ、その成果を会社や地域に還元してもらうことを目指していました。しかし正直まだそのレベルに至れていません。この段階で今以上に働き方のバリエーションだけを増やしても、意図した方向には向かわないので、今は働く人の“意識”にどうフォーカスを当てていくかを人事では議論しています。
決してがむしゃらに働くだけではない、また効率だけでも測れない、自分なりの成果の出し方や働きがいへのアプローチ。その深掘りを促進するには、「働き方の選択肢」があるだけでは足りないのだと藤田さんは考えています。

藤田さん
まだまだ多くの従業員の中には『製造業というものへのレッテル』があるのだと思います。例えば製造部門だから在宅勤務はできないという人がいますが、他社の製造業でも課長が在宅勤務しているケースはあります。『できない』ではなく、目的のために『どうすればできるのか』という議論をする方が健全で、そこから工場の全自動化のような話にも展開するかもしれません。私にとって、働き方改革も含む『変革』とは、自分自身や仕事に対するレッテルを剥がしていくことです。どうすれば手前にある固定観念を覆し、本質的なところに思考を向けられるか、人事としてはそこに働きかけていきたいと思っています。評価制度を変えていくこともその一助になるでしょうね。
究極は、パーパスだけでいいはずだ
最後に、ソミックをどんな組織に変えていきたいかをお聞きしました。
藤田さん
もっと流動性のある組織になればいいなと思います。先ほどのレッテル剥がしとも通ずるのですが、『これはあっちの部署の仕事だよね』と業務内容と部署を強固に紐づけるような発言を社内では割と多く聞くんです。もちろん責任の所在は明確であるべきですが、あまり『自分の仕事はここまで』『ここからは他部署の仕事』と決め切らず、皆がいろんなことをしてもいいと個人的には思っていて。また役職に対しても『部長は全員これをやらねばならない』『課長なんだからこういうことは知っていないといけない』というような決めつけをせず、パーパスを軸に役割をもう一度定義しても良いと思っているんですよね。いや、もういっそ定義すらせず、人事制度もなく、パーパスだけを共有してみんながパーパスに向かって一斉に働けるのが理想ですけど、そうもいきませんので……!

人事制度否定派の人事!?一見過激派な発言の裏には、人事を志した時の熱い思いがありました。
藤田さん
子どもの頃に見た、東京の満員電車から降りてくるサラリーマンたちがみんな下を向いている光景がずっと胸に残っているんです。チャップリンのモダン・タイムス*を見た時も、こういうのは嫌だと思った。この現状を変えたい、働くことにもっと人間の自律性を取り戻したいと思って私は人事をしています。
*1936年に発表された、チャールズ・チャップリンが監督・製作・脚本・作曲を担当した喜劇映画。資本主義社会や機械文明を題材に取った作品で、労働者の個人の尊厳が失われ、機械の一部分のようになっている世の中を笑いで表現している。
会社や地域への貢献と、その手前にあるチャレンジできる風土。そしてそのさらに前提となる、一人ひとりにパーソナライズされた働き方と、自律性を引き出していく仕組み。これらが全て組み合わさり、変革が成し遂げられる日まで、藤田さんたちの挑戦は終わりません。